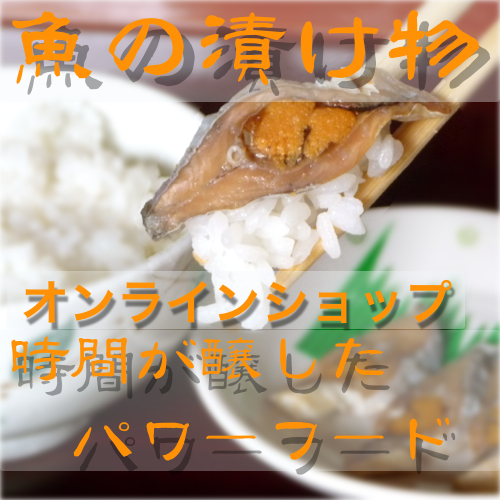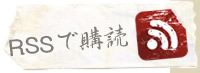ややこしや〜♪ ふなずしや〜♪
2009年10月30日
ふなずしと言葉に出してみれば言い方は一つしかありませんが
文字にしてみれば色んな書き方があります、といいますか
流通しています。
フナズシ、フナ寿司、鮒寿司、ふな寿司、鮒鮨、ふな鮨、
ふなずし、鮒すし、鮒鮓、funazushi、hunazushi
それぞれの表記にgoogleの画像検索のリンクを貼ってみました。
どれもちゃんと「ふなずし」です。
ちなみに寿司、鮨、鮓に意味の違いがあるのか?ですが
以前にもブログで紹介しましたが、小泉武夫氏の
著書『発酵』によると、紀元前4〜3世紀の成立と
いわれている中国最古の辞典『爾雅』のなかに既に
すしの記述があるとのことです。
それによると
「鮓(さ)」は魚の発酵貯蔵品
「鮨(し)」は魚の塩辛
「醢(かい)」が肉の塩辛
と区別されているようです。
「寿司」は江戸末期に作られた当て字だそうですね。
ということで、「ふなずし」の「すし」を表す漢字としては「鮓」が
意味合いとしては適しているとだと思います。
しかし、情報検索の量としてみた場合、例えばgoogleで
それぞれの字を検索してみると
「鮓」 :約 334,000 件
「鮨」 :約 5,380,000 件
「寿司」:約 35,100,000 件
と圧倒的に「寿司」の字が流通しているんですね。
意味と流通の間で「ふなずし」には色んな表記が乱立するような
状態になってしまったのでしょうかね。
ちなみに私のスタンスは「鮒寿司」で通していますが、
紹介や引用の場合はその元の表記を使うことにしています。
余呉湖畔の料亭は「徳山鮓」、滋賀県の広報記事には「鮒ずし」
マキノの魚治は「鮒寿し」という表記が使われています。
その位にバラバラなんですね。
ややこしや〜!
<内部リンク>
(私が読んだ)鮒寿司について書かれた本